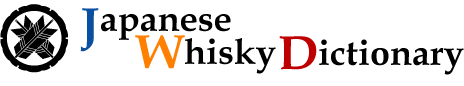世界のウイスキーから見えてくるジャパニーズウイスキーの魅力とは?
グラスに注がれたウイスキーは、世界中どこの国でも同じように見える。
けれど香りをひと口ふくめば、その土地の風が、気候が、人の気質が、それぞれの国が確かにそこに宿っている。
スコットランドの霧と風土、アイルランドの長い夜、ケンタッキーの熱気、カナダの寒風、日本の四季。
世界5大ウイスキーと呼ばれるこれらのスタイルは、単に製法の違いではなく、
それぞれの土地の文化が生み出した味わい。世界から日本のウイスキーに魅力を読み解いていきます。
アイリッシュ:クリーン&スムース、その美学
スコッチと並び、世界最古のウイスキー文化を持つアイルランド。
ブリテン島の西に浮かぶこの緑の国では、ウイスキーは古くから“生活の中の酒”として親しまれてきた。
「命の水(uisce beatha)」という言葉も、ウイスキーの語源としてこの地で生まれたとされています。
原料には、発芽させた大麦麦芽(モルト)と未発芽の大麦が一般的に使われています。
さらに蒸溜所によっては、ライ麦やオーツ麦などの穀物を加えることもあり、穏やかながら豊かな穀物香をもたらしている。
アイリッシュウイスキーを語るうえで欠かせない特徴が、三回蒸溜です。
17〜18世紀、粗野で雑味のある密造酒が多かった時代、品質を高めようと試みた職人たちが、蒸溜をもう一度重ねたのが始まりとされる。
その結果、よりクリーンで滑らかな酒質が生まれ、その名声を築いたとされています。
また、スコットランドのようにピートをほとんど使わない(※一部例外を除く)ため、香りは穏やか。
そこに果実のような甘やかさが加わり、味わいは軽やかで親しみやすい。
ジェムソンやブッシュミルズといった銘柄はその代表で、スムースでフルーティーなバランスが特徴だ。
アイリッシュウイスキーの魅力は、何よりも飲みやすさにあります。
ウイスキーに慣れていない人でもスッと受け入れられる柔らかさ。ストレートはもちろん、水割りやハイボールでも崩れにくく、日常のどんなシーンにも寄り添う。
生クリームを浮かべたホットカクテル「アイリッシュコーヒー」はこのウイスキーを使用する象徴的なカクテルでもあり、寒い夜にぬくもりを与えてくれる1杯です。
このウイスキーには、笑顔と音楽が似合う。パブでは毎日演奏やお客同士での合唱が行われている。
「アイリッシュウイスキー」の滑らかさは、飲み手の心までもほどいてくれているよう。
スコッチ:多様性と伝統が育む、ウイスキーの原点
日本のウイスキーのお手本ともなっているスコッチ。ブリテン島北部、スコットランドでつくられるこのウイスキーは、世界のウイスキー文化の原点とも言える存在です。
スコッチウイスキーには、モルトウイスキー、グレーンウイスキー、そしてそれらを組み合わせたブレンデッドウイスキーなど、多様な種類があります。
心地よく香り立つモルトと、味わいの下支えをする力強いグレーン。それぞれの個性が織りなす調和こそが、スコッチの魅力の一つです。
特定の地域内で厳格な規制に則って生産されていますが、その香味設計やスタイルには言及されていません。
そのため、地方ごとにも個性が際立ちます。
アイラ島のようにピート(スモーキー)が効いたもの、スペイサイドのように華やかでフルーティーなもの。スコットランドという土地の多様な風土が、香りの差異を生み出しているのです。
一言でスコッチを語ることは容易ではありませんが、基本的な工程は共通しています。
大麦麦芽を(蒸溜所によってはピートを使って)乾燥させ、銅製ポットスチルで二度蒸溜。
その後、最低3年間オーク樽で熟成を行います。
冷涼で湿潤なスコットランドの気候では、熟成がゆっくりと進み、味わいは非常に複雑になります。
アイラ島のラガヴーリンやラフロイグのように強烈なスモーキーさを誇るものもあれば、スペイサイドのグレンフィディックのようにフルーティーなタイプもあります。
そして、スコッチの香味を語るうえで欠かせないのが「シェリー樽」との出会いです。
スコッチのシェリー樽熟成は、18世紀のスコットランドで、密造業者が重税を逃れるためにシェリーの空き樽にウイスキーを隠したことから、偶然始まったとされています。
数年後にそのウイスキーを飲んでみたところ、これまでにない芳醇な香りとまろやかな味わいが生まれていたことが発見されたのです。
当時は偶然の選択に過ぎなかったものの、熟成を経た原酒からは驚くほど深みのある香りと甘やかな風味が生まれ、ウイスキーづくりの常識が変わりました。
多様性と伝統、そして偶然の発見。それらが織り重なって、現在の「スコッチウイスキー」を形づくっているのです。
アメリカン:フロンティアスピリッツが育くむ、力強く甘やかなウイスキー
ヨーロッパの伝統が息づくスコットランドやアイルランドに対し、アメリカのウイスキーは「新天地の酒」。
17〜18世紀、ヨーロッパからの大量の移民たちが大西洋を渡り、新大陸ケンタッキーやテネシーに根を下ろした。その際に祖国から蒸溜の技術を持ち込み、その地で手に入る穀物でウイスキーをつくりはじめました。
それがアメリカンウイスキーの原点であり、やがて「バーボン」という名で広く知られるようになります。
そして、この「バーボン」を名乗るためには、明確かつ重要な定義が2つあります。
・仕込みに使う穀物のうち、51%以上トウモロコシを使用する。
・焦がした新樽(チャード・アメリカン・ホワイトオーク)で熟成させる。
コーンの持つやわらかな甘みと香ばしさが、バーボンの骨格を形つくり、そこにライ麦がスパイシーなキレを、小麦が丸みとやさしさを、大麦麦芽が酵素とコクを加えていく。
それぞれの蒸溜所がこの「穀物比率(マッシュビル)」を独自に調整し、独自の風味設計を生み出している。
バーボンの香味を決定づけるもうひとつの鍵が、焦がした新樽である。
アメリカの広大な森で育ったホワイトオークの樽は、内側を火で焼かれ、木の内層がまるで真っ黒になるまで炭化させます。
その瞬間、樽の中ではリグニンやセルロース、木の成分が分解し、バニリンを生成。それがバニラやキャラメル、トーストした砂糖のような特有の甘香ばしい香りを生み出します。
新樽の使用は法律で義務付けられており、同じ樽を再利用することはできません。
その後はスコットランドや日本など、様々な国へバーボン樽として輸送され、また新たなウイスキーを熟成する樽として生まれ変わっていきます。
グラスへ注ぐと、甘いバニラ、カラメル、トースト、ナッツ等、まるで焼き立てのパンと焦がし砂糖が混ざり合ったような温もりのある香りが立ちあがります。
その〈一度きりの風味〉こそが、アメリカンウイスキーを象徴する「バーボンの魂」です。
力強くも甘く、ワイルドで温かい。この開拓者精神(フロンティア・スピリット)を映すようなバーボンの香りは、まさに“アメリカそのもの”の味わい。
樽を焦がす強い炎と乾いた西部の風を纏うウイスキーこそが「バーボンウイスキー」です。
カナディアン:軽やかさと調和のウイスキー
アメリカの北、厳しい寒さと雄大な自然に包まれたカナダ。
この国でつくられるウイスキーは、これまでのウイスキーの中でもひときわ穏やかで、どこか上品な気品を漂わせている。
その味わいは、極寒の気候と穀物の恵み、そしてブレンド文化の成熟によって育まれました。
カナディアンウイスキーの原料は、主にライ麦、トウモロコシ、大麦、小麦。
特にライ麦を多く使ったウイスキーはスパイシーでキリッとした香味を持ち、そこにトウモロコシ由来の甘みや滑らかさが加わることで、全体として非常にバランスの取れた味わいに仕上がります。
こうした穀物の組み合わせを生かし、複数の原酒を巧みにブレンドするのが、カナディアンウイスキーの最大の特徴だ。
他国では「ブレンド=複数のタイプのウイスキーを合わせる」ことを意味するが、カナダでは2種類に造り分けたウイスキーをブレンドが行われる。
| 酒類 | ベースウイスキー | フレーバリングウイスキー |
| 原料 | 主にトウモロコシ | ライ麦、ライ麦麦芽、大麦麦芽など |
| 蒸溜 | 連続式蒸留機を用いてアルコール度数約90%と高く蒸留。 | 単式蒸留機を用いて、アルコール度数を60〜70%程度で蒸留 |
| 特徴 | クセが少なく、ニュートラルな風味。 | 原料の穀物由来の豊かな風味が残る |
熟成にはバーボンと同じく、主にアメリカン・ホワイトオークの樽が使用されます。
近年では、バーボン樽やシェリー樽を使用する蒸溜所も多く、熟成庫では冬の寒さと夏の短い暑さが原酒をゆっくりと育てあげます。
寒冷地特有の穏やかな熟成環境が、口当たりのやわらかい、軽やかなウイスキーを生み出します。
代表的な銘柄には、カナディアンクラブ、クラウンローヤル、フォーティークリークなど。
いずれも滑らかで飲みやすく、ストレートでもハイボールでもその穏やかな個性を失わない。
穏やかな個性は他のスピリッツやリキュールとも相性がよく、カクテルのベースとしても重宝されています。
カナディアンウイスキーは、一言でいえば「調和のウイスキー」。
力強さや個性を競うのではなく、異なる味わいを一つに溶け合わせ、全体で美しく響かせる。
そこには、厳しい自然の中でも育まれる温もり、カナダという国の精神が映し出されているよう。
ジャパニーズ : 世界に誇る“調和の芸術”
スコッチの伝統に学び、アイリッシュを求め、アメリカンやカナディアンの自由な発想を吸収し、日本のウイスキーは、それらすべてを「ものつくり」の精神で再構築してきた。いまや世界五大ウイスキーの一角として、確固たる地位を築いています。
始まりは1920年代。
スコットランドで蒸溜を学んだ竹鶴政孝氏と、理想の味わいを追い求めた鳥井信治郎氏。
両氏が築いた「ニッカ」と「サントリー」という二つの潮流は、日本のウイスキー史の礎であり、
「スコッチに並ぶ本格ウイスキーを日本で」という夢は現実に変わりました。
ジャパニーズウイスキーの最大の特徴は、調和(ハーモニー)にあります。
気候、風土、そして人の感性までもが細やかに響き合い、一本のボトルの中に繊細かつ複雑な香味のグラデーションを描きます。
それは単なるブレンドではなく、まるで茶の湯や懐石料理のようま、素材の持ち味を損なわずに美しく調和させる美学があります。
近年制定されたジャパニーズウイスキーの定義には、原料には必ず麦芽使用し、日本で採水された水を使用。樽に関してはオークだけという縛りはなく、木製樽を使用し、糖化から瓶詰めまでを全て日本国内で行うことが定義されました。
また、日本は緯度と経度の差が大きく、地域ごとに特色があるのもスコットランドに似ています。
基本的には、冬は厳しく、夏は蒸し暑い。気候の振れ幅が熟成を早め、原酒に深いコクと香りをもたらします。
樽の特徴といえばなんといってもミズナラ樽。
ミズナラ特有の伽羅(きゃら)や白檀を思わせる香木のような香りは、「オリエンタルな余韻」として世界のウイスキーファンを魅了してやまず、近年はスコッチウイスキーにも使用されています。
また、定義にも「オーク」という縛りを設けず、「栗樽」「桜樽」の様に日本ならではの木材の使用にも余地を置いています。
また、スコットランドのように蒸溜所間で原酒を融通し合う文化はなく、日本の各蒸溜所は各地域に蒸溜所を建設し、多種多様な原酒を1社ごとに造り分ける技術を発展させてきました。
さらに、各社のブレンダーの手によって数え切れないほどの香味バリエーションが生まれ、一滴の中に緻密な構成美を宿すようになっていきました。
国内の代表的な銘柄には、山崎、白州、響、余市、宮城峡、そして新世代のクラフトウイスキー蒸溜所。
ジャパニーズウイスキーと海外で認知されている銘柄には、派手さよりも繊細さがあり、主張よりも調和を重んじる。そんな精神性のこもった造りが海外でも人気を博しています。
いまや世界のコンペティションで数々の栄誉を手にし、世界中のバーで静かに注がれる日本のウイスキー。
スコッチの模倣ではなく、ひとつの文化として確立した存在となりました。
四季の温度差が熟成を早め、湿度がまろやかな口当たりを生み、多種多様な原酒と独自のブレンド技術。
一滴の中に、「自然」「技」「心」が共存する。
比較の果てに見える「ジャパニーズイスキーの魅力」
五大ウイスキーの中で、日本だけが「他国の技術を継承し、独自に昇華した文化」。
スコッチの深み、アイリッシュの滑らかさ、バーボンの力強さ、カナディアンの穏やかさ
世界のウイスキーと比べることで、ジャパニーズウイスキーの独自性がより鮮明になってきました。
日本のウイスキーは、華やかさや力強さで突出するのではなく、調和と緻密さによって輝いています。
異なる原酒の品質向上に努め、樽香を巧みに組み合わせ、全体として美しく整えるその手腕は、まさに日本人ならではの美意識の表れ。
国際的な酒類コンペティション「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ(ISC)」では、
サントリーの「山崎」ブランドが、ウイスキー以外も審査に入る全部門での最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を、なんと3年連続で受賞し、「ISC」史上初の快挙を達成しました。
比較の果てに見えてくるのは、「静かで繊細ながらも、四季による力強い熟成、奥深く豊かな存在感」。
職人の技、四季の風土、文化と品質の積み重ねが感じられる。
それこそが、ジャパニーズウイスキーの真の魅力なのではないでしょうか。