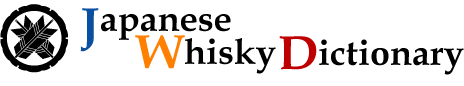福島県郡山市。郡山駅から5キロほどに位置する、歴史ある笹の川酒造の敷地内にあるのが、安積蒸溜所です。
今回の訪問では、ゼネラルマネジャーの鈴木巧様、そしてヘッドディスティラーの黒羽祥平様にご案内いただきました。
笹の川酒造とウイスキーの歩み
母体である笹の川酒造は、もともと日本酒の蔵元。創業は江戸時代に遡り、1765年(明和2年)に酒造り、販売を始めました。
戦後間もない1946年には、駐留していた米軍がウイスキーを飲んでいる姿に触発され、自社での製造を開始しました。
「チェリーウイスキー」のブランドは、社名の由来でもある「山桜」から取られたもの。長らく地ウイスキーとして親しまれてきましたが、2015年、創業200周年を機に「YAMAZAKURA」ブランドでの本格的な再スタートを切りました。
 |
 |
 |
 |
まず案内いただいたのは、来客用のスペース。
古い漆喰の建物を改装し、窓越しにポットスチルが眺められる造りになっています。木造の梁、土壁、石畳の床が織りなす空間は、伝統と現代的な蒸溜所の融合を感じさせるものでした。テーブルや試飲用のスペースも整えられており、訪れる人々を温かく迎える雰囲気があります。
製造設備と仕込みの特徴
 |
 |
 |
 |
蒸溜設備が入るのは「三番蔵」と呼ばれる建物。かつては瓶詰め前の焼酎や日本酒タンクで埋め尽くされ、さらに遡ればブドウジュースの製造も行われていたという、歴史の積み重なった空間です。
 |
 |
仕込みはワンバッチ400kgのモルトを使用。
粉砕比率はハスク2、グリッツ7、フラワー1。粉砕後のモルトは手作業でサンプリングし、丁寧に比率を確認。
英国クリスプ社製のモルトを中心に製造。ドイツ製やニュージーランド製のものも少量使用した経緯もあるが、安定して味もよいクリスプ社製が蒸留所としてはメインに使用。
秋口からは津波被害で塩害地域である宮城県沿岸部の大麦や、栃木の有機栽培麦の導入も計画中。東北の復興と農業支援への強い想いが込められています。
1日1バッチ、年間250バッチ程製造を行い、6,7,8月のみピーテッドを50バッチ、それ以外の期間でノンピートを200バッチ製造。今回の訪問時は、ちょうどピーテッドの製造が終わり、メンテナンスの期間でした。
 |
 |
 |
 |
三宅製作所製のマッシュタンにて、麦汁は一番1000L、二番1000Lの合計2000Lを得て、清澄度の高い麦汁を回収することで、エステリーで華やかな酒質を生むとのことでした。
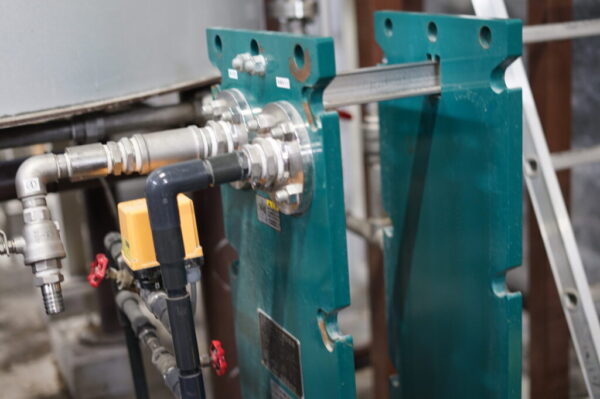 |
 |
発酵:木桶への転換
 |
 |
以前はステンレス製で、蒸溜設備と同じ室内で発酵を行っていましたが、温度変化に弱い菌の存在や発酵不良のリスクがあったため改良を決断。
発酵タンクは2019年から日本木槽製のダグラスファー(ベイマツ)材の木桶を導入。樹齢は500年に及ぶ木で、樹齢に沿って年輪の密度 が高くなり、非常に頑丈。壁を設けて発酵室を専用でつくり、温度を一定に保つ工夫がなされました。
木桶導入後は、発酵時間を70〜80時間から100時間超へ延長し、ボリューム感と複雑さが増した酒質が得られるようになったといいます。
夏場は24℃に管理された発酵室で一定の温度を保ち、急激な変化を避けています。伝統的かつ科学的なアプローチが共存する工程でした。
訪れた材にはメンテナンス期間であり、水を張って木槽タンクのメンテナンスが行われていました。
何日かに一度水を張り替えますが、その際にもウイスキーにとって有用な産膜酵母の様なものが形成されており、木槽も酵母や菌が住み着いて少しづつ成長しているそうです。
シングルモルト安積2025Editionからこの木桶が使用された原酒が一部使用されています。
内部は撮影禁止の為、木桶のサイズ感などはBSフジのウイスキペディアなどを参考にしてください。
蒸溜 : 『ゆっくり』へのこだわり
 |
 |
 |
 |
ポットスチルは初留器2000L、再留器1000L。秩父第一蒸溜所や長濱蒸溜所と同規模です。
ストレートヘッドに下向きのラインアームは他の蒸溜所に比べて太く短い。
この設計は社長の山口氏と三宅製作所で話し合い、長期熟成が可能なリッチで重厚な酒質を狙って作られました。
特徴的なのは、蒸溜の「火加減」。
かつては強火で行っていた工程を、2021年からは弱火でじっくりと進めるようになりました。
これはスコットランド・グレンゴイン蒸溜所の「The slowest distillation in Scotland(スコットランドで最も遅い蒸溜所)」の造りに共感し、銅製のスチルとの接触時間を長く保つことで、オフフレーバーを取り除き、よりクリーンでフルーティーな酒質を目指した結果だといいます。
チームと職人の協働
ウイスキーの製造スタッフはわずか3名。
各自が全工程を習得し、1人で1バッチを担当します。小規模だからこそ全体を把握し、意見を交わしながら改善を重ねる体制が築かれていました。ここに安積蒸溜所の柔軟さと強さが表れています。
熟成とマリッジ、桜樽への想い
 |
 |
ウェアハウスは現在2棟、合計約1500樽を貯蔵。最長で2017年製造の原酒が眠っています。
熟成庫はもともと瓶詰めライン設備を改修した建物。エンジェルズシェアは4〜5%。
年間40℃もの寒暖差が熟成に影響を与えています。今後は創業地でもある猪苗代湖近くの廃校を第三熟成庫として活用する計画もあるそうです。
樽の比率はバーボン樽が全体の8割、その他シェリー、ミズナラ、ワイン、地元のクラフトビールと協業で造られるIPA樽等様々。

特筆すべきは熟成庫内にある巨大な1万リットルのマリッジタンク。アンメリカンホワイトオーク製のこのタンクは、『安積&4』をブレンド後に3ヶ月間原酒を落ち着かせる為にあります。
全体の1/5程をボトリングし、その後再充填を繰り返すソレラシステムの様につぎ足しを行い、安積ならではの「&4」シリーズの骨格を形づくっています。
さらに、県内流通の&4桜樽フィニッシュなど、挑戦的な取り組みも進行中。
桜樽は非常に強い香りを放ち、通り過ぎただけでもその存在を感じるほどだそう。ブランド名「山桜」への深い思い入れが、桜樽へ込められていました。
訪問を終えて
「磐梯おろし」が吹き降ろす『風の蒸溜所・安積蒸溜所』。
日本酒の蔵として200年の歳月を歩み、戦後に芽生えたウイスキーづくりの夢を引き継ぎ、そして今、東北の大地と共に未来を描いている。そこには伝統が静かに息づき、熟練の手仕事と新しい挑戦が調和していました。
趣のある建物、木の香り漂う発酵槽、静かに長く蒸溜を行う小さなポットスチル。少数精鋭のチームが互いの知恵を重ね、一本のボトルに心を込める姿には、ものづくりの原点のような力強さが宿っています。
このウイスキーもまた、土地の記憶、人々の情熱、そして未来への思いが溶け合った一雫です。
ウイスキーの業界全体が苦境に立たされた時代。笹の川酒造は、かつての羽生の原酒を預かりました。
その行為は単なる保管ではなく、作り手の想いと共に「時」を守り抜く意思。
失われるはずだった一滴を、未来へつなぐ姿勢は、かつて日本のウイスキーを牽引した東亜、そしてチェリーという存在だからこそできたこと。
そしてその想いは、秩父と安積を結ぶ見えない糸として、今も息づいています。
そして安積蒸溜所は今も進化を続けています。そのウイスキーに触れた瞬間、東北の風土と人の想いが、ゆるやかに胸へと染み渡っていきました。
最後に:ジャパニーズウイスキーのおすすめ書籍
世界的なトレンドを巻き起こしている「ジャパニーズウイスキー」の事をもっと知りたい、もっと勉強したいという方は、是非こちらの書籍をおすすめいたします。
(1).Whisky Galore(ウイスキーガロア)Vol.51 2025年8月号
【巻頭特集】
「スコッチ蒸留所名鑑 第2弾 ペルノリカール[前編]」
フランスのペルノリカール社が所有するモルト蒸留所について解説し。今号では計6つの蒸留所を掲載。
【特集】
「国家級中国威士忌最新事情 ダイキン編」
土屋守編集長が中国を訪れ、目覚ましい成長を遂げるチャイニーズウイスキー最新事情をリポート。
「韓国ウイスキー」
モルトウイスキー蒸留所が相次いで誕生している韓国を訪問。
【特別対談】
7年ぶりに誕生した新定番 ジョニーウォーカー ブラックルビー
土屋守×金子亜矢人ベンツェ氏
【イベントリポート】
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2025 受賞結果
(2).ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー
世界的にも有名なウイスキー評論家で、ウイスキー文化研究所代表 土屋守先生の著書「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」です。
ウイスキーの基礎知識、日本へのウイスキーの伝来、ジャパニーズウイスキーの誕生、広告戦略とジャパニーズウイスキーの盛隆、そして、現在のクラフト蒸留所の勃興まで。日本のウイスキーの事が非常にわかりやすくまとめられた一冊。
(3).ウイスキーと私(竹鶴政孝)
日本でのウイスキー醸造に人生を捧げた、ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝。ただひたすらにウイスキーを愛した男が自らを語った自伝の改訂復刻版。若き日、単身スコットランドに留学し、幾多の苦難を乗り越えてジャパニーズ・ウイスキーを完成させるまでの日々や、伴侶となるリタのことなどが鮮やかに描かれる。
(4).新世代蒸留所からの挑戦状
2019年発売。世界に空前のウイスキーブームが到来しているいま、クラフト蒸留所の経営者たちは何を考え、どんな想いでウイスキー造りに挑んだのか。日本でクラフト蒸留所が誕生するきっかけを作った、イチローズ・モルトで有名なベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏をはじめとする、13人のクラフト蒸留所の経営者たちが世界に挑む姿を綴った1冊。
(5).ウイスキーライジング
2016年にアメリカで出版された『Whisky Risng』の日本語版であり、内容も大幅にアップデート。ジャパニーズ・ウイスキーの歴史が詳細に記述されているだけでなく、近年、創設がつづくクラフト蒸溜所を含む、日本の全蒸溜所に関するデータも掲載。そのほかにも、今まで発売された伝説的なボトルの解説や、ジャパニーズ・ウイスキーが飲めるバーなども掲載されています。
(6).ウイスキーと風の味
1969年にニッカウヰスキーに入社した、三代目マスターブレンダーの佐藤茂夫氏の著書。
『ピュアモルト』『ブラックニッカクリア』『フロム・ザ・バレル』の生みの親でもあり、なかでも『シングルモルト余市1987』はウイスキーの国際的コンペティションWWA(ワールド・ウイスキー・アワード)にて「ワールド・ベスト・シングルモルト」を受賞。
竹鶴政孝、竹鶴威の意志を引き継いだブレンダー界のレジェンドが語る今昔。