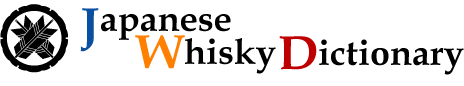かつて、ひっそりと国産ウイスキーを守り続けていた日本の蒸溜所。
10年前には10メーカーにも満たなかった蒸溜所であったが、今やその光景は一変し、まるで戦国時代の様相を呈している。
北海道から沖縄まで、大小さまざまなクラフト蒸溜所が続々と誕生し、ジャパニーズウイスキーは黄金期を迎えた。しかしこの熱狂は終わり、その先にあるのは、果たして繁栄か、それとも…
バーテンダーとして、ジャパニーズウイスキーを扱うサイトの記者として、クラフトウイスキーブームの行き先を、現状の課題と今後の可能性から整理していきたい。
1.原酒不足とクラフト蒸溜所
2000年代初頭、ウイスキー消費は低迷の一途をたどっており、大手は軒並み生産量を削減。この時期の原酒の不足が後の戦国時代に大きく響くこととなる。
2008年にはサントリーの仕掛けによる、いわゆる【ハイボールブーム】があり、若年層や女性にもウイスキーという選択肢が生まれることになる。
この時期に建てられたのが、日本のクラフトウイスキーの先駆けである「イチローズモルト秩父蒸溜所」。
そこから2014年度のNIKKAの創業者竹鶴政孝連続テレビ小説『マッサン』によりウイスキーブームは加速。
このあたりから原酒不足は深刻の一途をたどり、大手メーカーも『響12年』や『竹鶴17年』などの年数表記のあるウイスキーは軒並み終売となり、主力商品は年数表記のないウイスキーの販売に切り替えられていきます。
2016年、ウイスキーブームと原酒不足により、蒸溜所設立の動きが活発化。「クラフト蒸溜所元年」とも呼べるのがこの時期。
| 蒸留開始 | 蒸溜所 | 特徴・技術 |
|---|---|---|
| 2016 | 厚岸蒸溜所(堅展実業) | 日本のアイラとも呼べる土地。二十四節季シリーズ、醪造りの技術力、ピート、海霧を浴びる熟成庫 |
| 2016 | 静岡蒸溜所(ガイアフロー) | 閉鎖した軽井沢蒸溜所の蒸溜機、薪直火蒸溜機 |
| 2016 | 津貫蒸溜所(本坊酒造) | 本坊酒造第二蒸溜所、どっしりとした酒質と南国的な甘さ、屋久島に熟成庫 |
| 2016 | 安積蒸溜所(笹の川酒造) | 「山桜」ブランドから再始動。イチローズモルトとのつながり、地域に密着した多数の限定製品 |
| 2017 | 長濱蒸溜所(長濱浪漫ビール) | 日本最小規模の小型スチル。一日一醸。海外ウイスキーとのブレンド、コラボ販売 |
| 2017 改修完了 |
三郎丸蒸溜所(若鶴酒造) | クラウドファウンディングにて改修。鋳造制スチルZEMON。ヘビリーピーテッドに絞った生産。タロットカードシリーズ |
| 2017 | 嘉之助蒸溜所(小正醸造) | 焼酎蔵母体。三機のスチル、焼酎リチャーカスク。現在は焼酎蔵でグレーンも製造。 |
| 2017 | 桜尾蒸留所(SAKURAO B&D) | 海沿い熟成の「桜尾」とトンネル熟成の「戸河内」。ハイブリットスチルによる原酒造り分け。ジンも人気 |
先駆けて蒸溜を開始したこれらの蒸溜所は「ニューメイク」や「ニューボーン」、もしくは「ジン」の販売、もしくは、以前より販売していた酒類を継続して売ることで資金面での問題をクリアしており、安定した収益構造となっている。
樽の販売等、管理の難しいものに関しては一部の蒸溜所は行っているものの、多くの蒸溜所は自社で手掛けたシングルモルトやブレンデッドの販売をメインにしている。
2.「フェイク」の存在と「本物」への渇望。法整備の進展
2021年、日本洋酒酒造組合によって「ジャパニーズウイスキー」の定義が初めて明文化された。
原材料から製造、貯蔵、ボトリングに至るまで、一定の基準が設けられたことは、消費者にとって大きな前進といえる。
とはいえ、これはあくまで“自主基準”であり、法的拘束力はない。モラルに欠ける事業者が抜け道を突き、「フェイク・ジャパニーズ」を巧妙に販売し続ける可能性は今なお残されている。
実際、海外の品評会に出品された製品の中には、ラベルに記された蒸溜所で本当に蒸溜されたのか疑わしい事例も見受けられる。こうした疑念が生まれるのは、一部の蒸溜所への不信感が業界全体に影を落としているからに他ならない。
一方で、ウイスキーを深く理解する消費者は、すでに「誠実さ」を見抜く目を持っている。もはや、見せかけのラベルやマーケティングだけでは通用しない時代だ。
とはいえ、ライトな層にとっては「安くて美味しければそれでいい」という声も根強い。すべての消費者が産地や製法にこだわるわけではないのも現実である。
それでも、あえて漢字のラベルを選び、「国産」と信じてボトルを手に取る。そこには、日本のものづくりへの信頼と愛着が込められているからだと感じる。
そこへつけこむ「フェイク・ジャパニーズ」は個人的には度し難く、許しがたい。
「本物のジャパニーズウイスキーとは何か」という問いに、業界全体で明確に答えていくこと。その基準づくりこそが、クラフト戦国時代を終わらせ、ジャパニーズウイスキーが次のステージへと踏み出す鍵となるのではないだろうか。
3.「風土」「伝統」「誇り」クラフト蒸溜所に求められる哲学
厚岸の「四季と熟成環境」、三郎丸の「ピートを極める」、嘉之助の「原酒の造り分けと焼酎カスク」。
今、日本のクラフトウイスキー界で頭角を現している蒸溜所は、いずれも一貫して「土地」「文化」「哲学」に根ざした明確なアイデンティティを持っている。
■ 厚岸蒸溜所:アイラ、憧れのその先へ。テロワールが育む季節の物語
北海道・厚岸は、広大な湿原、潮の香りを運ぶ風、豊かなピート層とその水系に恵まれた、ウイスキー造りに理想的な地。牡蠣の産地としても知られ、海と共に生きるその風土は、アイヌの時代から今も息づいています。
醪(もろみ)造りにおいても他にはない繊細な管理と技術を駆使し、その仕込みは極めて丁寧で緻密。HACCPによるウイスキーにおける衛生管理も大きなポイント。
「良い原酒(ニューメイク)なくして、良い熟成は生まれない」と、蒸溜前の段階から品質を突き詰めています。
その結果として生まれるニューメイクは、すでに完成された一滴とも言えるほどの完成度を誇り、熟成後も高い品質が約束されたものとなります。
また、この地の気候、四季によって大きく変化する温度と湿度、海霧の出る環境は、ウイスキーの熟成に驚くほどの複雑で多層的な表情を与えます。
蒸溜から熟成、瓶詰までを一貫して行い、オール厚岸ウイスキーへ向かう姿勢は、「ウイスキーにもテロワールがある」という強い信念の表れでもあります。
熟成には、北海道産のミズナラを使った樽も使用。海辺に佇む熟成庫では、潮風が樽の呼吸を通じてしみ込み、ウイスキーに潮のニュアンスをもたらします。それはまさに、厚岸の自然そのものを纏った一杯。
そんな哲学の結晶ともいえる「二十四節季シリーズ」も、蒸溜所の歩みと共に驚くべきスピードで進行し、まもなくひとつの節目を迎えようとしています。
■ 三郎丸蒸留所:Ultimate Peat、タロットカード・スピリッツ(魂)の成長の旅
「富山でしか造れない、唯一無二のウイスキーを。」
富山県砺波市に位置する三郎丸蒸溜所は、地域の伝統技術と現代的革新を融合させたウイスキーづくりを一貫して追求。
鋳物の町・高岡ならではの世界初の鋳銅製ポットスチル「ZEMON(ゼモン)」は、その象徴的存在であり、地元鋳造技術と蒸溜工学の融合。
さらに、使用済み樽の修理・再生を行う「Re:COOPERAGE」プロジェクトを通じ、サステナビリティと資源の循環を両立させた地域密着型のウイスキー製造を実現しています。
また蒸溜所の大きな特徴として、香味設計の軸をピーテッドモルトに絞っています。
スモーキーなアロマは好みが分かれる領域ですが、あえてその個性を主軸とし、その個性を愛する熱狂的ファンの支持を集め、高く評価されています。
また、リリースごとに物語性を持たせた「タロットカードシリーズ」は、“スピリッツ=魂”の成長をテーマとし、各リリースごとに設備・原料などに段階的な変化を取り入れることで、ウイスキーの進化と、蒸溜所そのものの成熟過程を追体験するような物語があります。
■ 嘉之助蒸溜所:南国の風土が育む、伝統と革新の融合
鹿児島県日置市、吹上浜。日本三大砂丘のひとつに面したこの地に、嘉之助蒸溜所は佇んでいます。南国特有の温暖な気候と、海から吹き込む風。この土地ならではの自然環境が、ウイスキーの熟成において他にはない個性をもたらしています。
急峻な寒暖差がない代わりに、南方の柔らかな陽気と塩気を含んだ潮風が交差する熟成庫では、短期間でフルーティーで豊かな香味をもつウイスキーが育ちます。その熟成スピードと香味の幅広さは、国内でも際立った特徴のひとつです。
クラフト蒸溜所としては珍しく3基のポットスチルを保有。それぞれ異なるサイズ・形状のスチルを使い分けることで、原酒のボディや香りに多層的なニュアンスを加えることが可能になります。
軽やかで華やかなタイプから、厚みと深みのあるヘビータイプまで、幅広い個性を生み出します。
発酵・蒸溜の工程では、母体である小正酒造が長年培ってきた焼酎造りの技術が活かされており、薩摩に根差した酒造文化と、世界基準のウイスキー製法が融合した独自のスタイルが確立されています。
さらに嘉之助蒸溜所ならではの特徴として注目すべきが、「焼酎リチャーカスク」です。
これは、小正酒造2代目・小正嘉之助氏が1951年に開発し、現在も製造されている熟成焼酎「メローコヅル」にて使用した樽をウイスキー熟成に使用。バーボン樽やシェリー樽に加え、この焼酎樽によってもたらされるやわらかく甘いニュアンスは、嘉之助のウイスキーに特有の味わいを加えています。
トロピカルフルーツを思わせる南国感、ニッキや梅のような和のスパイス、焼酎由来の甘く柔らかなニュアンス。
嘉之助蒸溜所は、吹上浜の自然環境と薩摩の酒造文化、そして伝統的に培った技術をウイスキー造りに融合させることで、他にはないウイスキーを提供しています。
4.「物語」がなければ、もう売れない?
ジャパニーズウイスキーの市場は、一昔前の「蒸溜すれば売れる」時代から大きく変化しました。
現在、消費者は単なるラベルの美しさや一時的なイメージ戦略だけでは満足せず、より深い価値や背景を求めています。
味覚や品質だけでなく、「なぜこの場所で、なぜこの造りをするのか」という背景や造り手の思想に強い関心が集まっています。
情報感度の高いウイスキーファンは、製品のストーリーや造り手の哲学を積極的に調べ、共感できる「推し」ブランドを選ぶ傾向が強まっています。
もはやジャパニーズウイスキーはスコットランドの単なる模倣を抜け、様々な気候風土のある日本ならでは「ジャパニーズウイスキー」としての理由や哲学を持ち、独自の物語を語れる蒸溜所が、市場で存在感を発揮しています。
つまりはその背後にある“物語”の説得力まで含めて、ウイスキーの魅力が評価される時代になっています。
ただ美味しいだけではなく、地域性・歴史・造り手の情熱や信念を伝られることが出来るウイスキーは、「100年ブランド」として次世代へと受け継がれていくのではないでしょうか。
5. 世界輸出と評価 ― 「本物のジャパニーズ」をどう伝えるか
世界的なジャパニーズウイスキーブームに後押しされ、今や多くの蒸溜所が輸出を視野に入れるようになった。実際、輸出量はこの10年で大きく伸び、日本のウイスキーは世界のバーで見かけるようになりました。
国際市場で確かな評価と販売を継続していくためには、単なる人気に乗るのではなく、「ジャパニーズウイスキーとは何か」という根本が必要ではないだろうか。
先にも書いた“フェイク・ジャパニーズウイスキー”の排除。
つまり、海外産の原酒を使用しながら「日本製」をうたうような製品と、真摯にウイスキー造りに向き合う国内蒸溜所の製品との線引きを明確にすることだ。2021年に策定されたジャパニーズウイスキーの定義は、その第一歩にすぎません。
そのうえで、今後さらに求められるのは、「品質と一貫性」、そして「ブランド哲学」。
単なる香味の評価を超え、“ジャパニーズウイスキーらしさ”とは何かを問い続けること。それは、気候・技術・文化・造り手の哲学、すべてを込めた一つの「物語」として、世界に語られてほしいだけの要素もある。
輸出とは、単にボトルを海外に届ける行為ではない。
スピリッツに込めた“魂”を、どこまで真摯に、どこまで誠実に伝えられるか。それが今後の鍵になるはずだ
6.戦国の終わりとは
戦国時代とは、淘汰と革新が交錯する時代だ。
今まさに日本のウイスキー業界は、そのただ中にある。
乱立したクラフト蒸溜所。熱狂と期待。その裏では、建設計画の白紙撤回といった“静かな敗退”も、じわじわと現れ始めている。
すべての蒸溜所が生き残るわけではない。
地域に根を下ろし、哲学を持ち、文化を背負いながら、誠実にウイスキーと向き合う蒸溜所たち。彼らこそが、次の100年を創る。
だからこそ、「戦国の終わり」とは競争の終わりではなく、「ジャパニーズウイスキーとは何か」が確立されるとき。それが世界に認知されるとき、そこにようやく平定が訪れる。
私たち消費者にも問われている。
目先なラベルや情報だけではなく、語るべき、聴くべき哲学に耳を澄ませる力があるかどうか。
哲学を持つ蒸溜所に敬意を払い、その蒸溜所を選択することが「次の100年のウイスキー」を育むともいえる