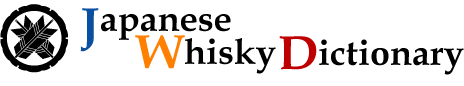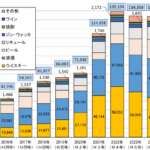ジャパニーズウイスキーのロゴマーク制定、法制化を目指し整備を開始。

画像引用:日本洋酒酒造組合
2021年2月に日本洋酒酒造組合の自主基準としてジャパニーズウイスキーの自主基準が制定されました。
その実効性を高めるため、2025年3月に「ジャパニーズウイスキーのロゴマーク」を制定、発表が行われました。
このマークが浸透することで国内外の購入者に「ジャパニーズウイスキー」の識別が容易になるというものです。
今後は「自主基準」の法制化に向け、酒類業組合法に基づく「地理的表示(GI)の指定」をめざします。
ですが、国内外で好調なウイスキー販売に水を差したくない、、、と国税庁は法整備化に関してはかなり消極的に感じます。
偽物の、海外原酒のみを使用していたり、ましてやウイスキー原酒が10%程のウイスキー風スピリッツを海外でジャパニーズウイスキーとして販売され、その味を日本のウイスキーと認知されるのは心苦しい。
過去にも、海外でのフェイクジャパニーズウイスキー販売が問題となっており、米ロサンゼルスやニューヨークなどの店頭では基準に満たしていないにも関わらず、【ジャパニーズウイスキー】と表記した商品が2割弱販売されているのが現状です。日本人が見れば明らかに漢字がおかしかったり、名前に違和感を覚えたりするものですが、もちろん現地の方には判別できません。
実際に筆者も海外のゲストに『日本のライスウイスキーを家で飲んでいる』と言われ、銘柄を聞くと聞いたこともありません。
調べてみると確かに【ジャパニーズウイスキー】と書いて販売されていますが、国内の製造元はウイスキーの製造免許を持っておらず、海外業者から委託されて製造を行っているとのこと。
実際の中身は米焼酎で、アメリカの酒税上は【ウイスキー】であり、【日本で蒸溜】を行っているため、ジャパニーズウイスキーとして販売しているようです。
このような模造品が海外で違和感のある変な名前、変な漢字、変な中身をウイスキーとして販売しています。未だに国内で数メーカーが加担しているのも現状です。
別の問題として、国内で製造したグレーンをブレンドすればジャパニーズウイスキーとなりますが、小規模蒸溜所ではなかなか難しいのが現状です。
多くの蒸溜所は
- シングルモルトに絞った製造
- 国内でグレーンも製造し、自社ブレンデッドを製造する
- グレーンを国内にて調達し、ジャパニーズブレンデッドとして製造する
- 海外グレーンを国内で3年以上熟成してブレンデッド用に使用する
この辺りが国内で行われています。
1.2.3.は問題なくジャパニーズウイスキーです。
2.は大きなメーカーなどでは容易ですが、2つ以上蒸溜所を構えているメーカーは国内でも少数です。同設備で別種の穀物を使用したグレーンを製造するのもかなり難しいようです。
3.は吉田電材蒸溜所のように、国内へのグレーン供給を明言している蒸留所なども登場しており、今後もそういった蒸溜所が登場するかもしれません。
4.に関してはサントリーやニッカもこのような製品を製造しており、多くのクラフト蒸留所が行っています。
これは組合の自主基準上では『ジャパニーズウイスキー』ではありません。ですが価格の面で安価になったり、蒸溜所のもつ個性のあるモルトと見事に融合させるブレンダーの方々の努力の形でもあります。
一概にすべてが悪ではなく、もはや倫理観の問題のような話になってしまうため、ここまで拗れてしまっていると感じます。
『ジャパニーズウイスキー』だけではなく、倫理観のある美味しい『国産メーカーウイスキー』も両方にいい形になるように、法整備化は今後も取り組まれていくことになりそうです。