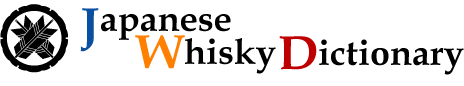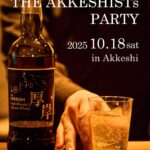1.樽の酒類について
樽は主に、
- 材木による違い
- 入っていた酒類による違い
この2点の違いで味わいや香味に関するプロセスが分かれます。
材木による違い
樽の素材となる木材は、熟成のプロセスにおいて酒と共に収縮を繰り返し、呼吸をすることで、その成分をじっくりと液体へ移していきます。
タンニンの量、含有オイル、香りの成分などが、酒の香味・色調・質感に影響します。
たとえばアメリカンホワイトオークは、ウイスキーにバニラやキャラメル、ココナッツのような甘くまろやかな香りを与えます。
一方、日本のミズナラ樽は、白檀や伽羅とも称されるオリエンタルな香りを生み出すことで、世界中のウイスキーファンに注目されています。
木材によってもたらされる香味は、いわばウイスキーの骨格です。この材が何かによって、熟成による表情の方向性が決まってくると言っても過言ではありません。
入っていた酒類による違い
もう一つの重要な要素が、その樽が「かつて何の熟成に使用されていたか」という点です。
バーボンやシェリー、ワインなどの酒が染み込んだ樽は、その香味成分を新たに熟成される酒に移し、独自の、より複雑なニュアンスをウイスキーへ加えていきます。
たとえば、バーボン樽は比較的香りが穏やかになり、酒本来の特徴を引き立てながら、ほのかな甘さやフルーティーさを引き出す傾向があります。
シェリー樽やポート樽では、その酒の残り香が強く、ドライフルーツやナッツ、濃厚な甘さと渋さを酒に加え、さらなる複雑さと奥行きをもたらします。
この「前歴」があることで、ウイスキーは単に木の味だけにとどまりません。
樽に染み込んだお酒の記憶が、まるで古い日記のように、新しい酒の中にじんわりとにじみ出るのです。
二つの要素が、ウイスキーの唯一無二の味わいを創る
樽のサイズ感や熟成スピード等、他にも熟成には様々な要素がかかわりますが、樽に焦点を当てると、
同じ木材でも、前に何の酒が入っていたかで全く異なる熟成過程を見せ、逆に同じ酒類が入っていたとしても、木の種類が違えばその香りの出方も変わってきます。つまり、木と前歴という二つの要素が交わることに、樽熟成の妙があります。
この差異を感じ、ウイスキーの骨格を決めることがブレンダーの腕の見せ所であり、ウイスキーづくりの芸術性とも言えます。
樽はただの入れ物ではなく、時間の中で味を育てる『もう一人の造り手』なのです。
2. 木材の種類による分類
→ 主にウイスキーに使用される木材は国内外合わせて8種類程度。現在は新たな価値を生み出す樽を求め、様々な木材で試験熟成が行われています。
3.木材がもたらす香味
アメリカンホワイトオーク
アメリカンホワイトオークは、ウイスキー熟成において最も広く使われる木材種であり、特にバーボンウイスキーでは、アメリカンホワイトオークの新樽のみを使用する規定があります。
スコッチ、ジャパニーズウイスキーにおいても主要な熟成樽素材です。
このオークは、北アメリカ(主にケンタッキー州、ミズーリ州、アパラチア山脈周辺)に自生する広葉樹で、ウイスキー樽材としては特に「バニリン」という香味成分に富み、甘く香ばしい熟成香をもたらすことで知られます。
アメリカンホワイトオーク樽由来の香味の一部を紹介すると、
バニラ、キャラメル、ハチミツ、メープルシロップ、焼き菓子等
バーボンに使用された後の空樽は、スコッチやジャパニーズウイスキーの熟成に再利用されることが多く、2nd Fillでは、香味成分が穏やかになり、よりフルーティーなアロマを引き出す傾向があります。
まさにアメリカンホワイトオークは、世界中のウイスキーにおいて“スタンダード”といえる木材です。
ヨーロピアンオーク
ヨーロピアンオークは、ウイスキー熟成においてアメリカンホワイトオークと並ぶ主要な樽材のひとつです。特にスコッチウイスキーの伝統的な熟成樽として広く使用されており、ジャパニーズウイスキーでも採用例が増えています。
主にフランスや東ヨーロッパを中心に自生する広葉樹で、アメリカンホワイトオークに比べて木目が細かく、含まれるタンニン(渋味成分)が多いのが特徴です。このため、ウイスキーに重厚でスパイシーな味わいを与え、熟成を通じて複雑な香味が育まれます。
ヨーロピアンオーク樽由来の香味の一部を紹介すると、
スパイス(クローブ、ナツメグ)、ドライフルーツ(レーズン、プルーン)、チョコレート、コーヒー等
また、シェリー樽として使用されたものも多く、シェリー由来の豊かな甘みや果実味が加わることで、より深みのある味わいを醸し出します。
ヨーロピアンオークは、その個性的な風味と熟成効果から、ウイスキーに多様な表現をもたらす重要な樽材として世界中で重宝されています。
ミズナラ
ミズナラ樽とは、東アジアに自生するブナ科の落葉広葉樹「ミズナラ」を素材とするウイスキー熟成樽のことを指します。日本では北海道から本州にかけて広く分布しており、ウイスキー樽としての使用は、1940年代の戦時中、欧州産の樽材が入手困難になった際に使用が始まりました。
ミズナラ材は繊維が粗く、水分を多く含みやすいため、加工が難しく漏れやすい為、製造には熟練の技術を要します。「ジャパニーズウイスキーを象徴する樽」として、国内外で認知が上がってきています。
ミズナラ樽で熟成されたウイスキーには、他の樽では得られない東洋的な香りと評される香りが現れます。
ミズナラ樽由来の香味の一部を紹介すると、
白檀、伽羅、香木、スパイス、メロン、ウッディネス等
新樽においては木の香りがかなり強く、スパイシーな風味がよく現れます。10年以上の長期熟成や何度か使用することによって、穏やかな香味成分が抽出されることで、甘さ・スパイス・木香が調和した奥深い風味が形成されます。
ミズナラ樽原酒は単独でも強い個性を持ちますが、ブレンドの中では味わいに『木香やオリエンタル』な香りを与えます。
前述のように加工や漏れが出やすい為、後熟(フィニッシュ)に使用されることが多い樽。
しかし近年では、大手メーカーがミズナラ樽100%熟成のシングルモルトの様な限定リリースも登場しており、希少性が高い存在として、世界の蒸溜業界から注目を集めています。
フレンチオーク
フレンチオークは、主にフランスの森林に自生しています。ウイスキーやワイン、ブランデーの樽材として世界的に高く評価されています。
フレンチオークは、樽材として密度が高く、タンニン含量が豊富であり、熟成中には深みのあるスパイシーさと、しっかりとした渋味、芳醇な木香がウイスキーへと移ります。
フレンチオーク樽由来の香味の一部を紹介すると、
スパイス(タンニン、クローブ、シナモン)、レーズン、イチジク、 タバコ、レザー、カカオ等
ウイスキーでは、シェリー樽や赤ワイン樽として輸入されることが多く、スコッチやジャパニーズウイスキーのブレンドの個性、香味に深みと厚みをもたらし、ウイスキーの「奥行き」や「重厚感」を生み出す要素として機能します。
スパニッシュオーク
スパニッシュオークとは、主にスペイン北部に分布するヨーロッパ産のオーク材を指し、伝統的にシェリー酒の熟成樽として用いられてきた材です。
分類上はフレンチオークと同じ種ですが、育成環境の違いにより香味成分も変わっています。
高タンニン、多大な抽出成分を持つため、熟成されたウイスキーには色が濃く映り、力強く濃密な香味が加わります。
スパニッシュオーク樽由来の香味の一部を紹介すると、
ドライフルーツ(レーズン、プルーン)、クローブ、レザー、黒糖、ダークチョコレート、バルサミコ様の酸味
国内で「Spanish Oak」という呼称が使用される場合は、新樽として輸入されてきたものを指します。
新樽に近い状態での使用では、強いタンニンと木香が際立ち、長期熟成を経ることで渋みが丸くなり、重厚でスパイシーでタンニンを多く含んだ風味が構築されます。
その香味傾向から、単体使用ではなく、シェリー樽に使用されたのちの使用、もしくは他の樽原酒とのブレンドで「深み」や「どっしりとした質感」を与える役割として使用されています。
栗
栗樽とは、近年、一部の蒸溜所により、ウイスキーの熟成や後熟(フィニッシュ)にも応用される例が現れています。
栗材は、タンニン含有が豊富で、硬く加工しずらいデメリットもありますが、独特な風味を生む材として国内外で注目が集まっています。
栗樽由来の香味の一部を紹介すると、
焼き栗、焼き芋、メープル、土っぽさ、ローストナッツ
ウイスキー分野での使用は非常に限定的ですが、かつてはジェムソンから発売されたりと、一部の蒸溜所において、限定商品や特別リリースの一部として試験的に使用されています。
製樽が難しく希少であること、またその香味傾向から、単体使用ではなく、他原酒との組み合わせで使用されることが多く、今後注目の木材とも言えます。
桜
桜樽とは、日本に古くから自生・植栽されるバラ科サクラ属の木材を用いて製作されたウイスキー熟成用樽のことを指します。国内の代表的な品種にはヤマザクラなどがあり、家具や楽器、和樽材としても使用されてきた日本独自の木材です。
桜材は、日本国内での樽材としての利用は非常に稀であり、限定商品などで一部使用されています。製樽用木材としての流通量が少なく、また加工が難しいため、希少な存在と言えます。
桜樽由来の香味の一部を紹介すると、
桜餅、シナモン、ローズウッド、赤いベリー、穏やかなタンニン
桜材は、甘く柔らかい「桜餅」に似た香りと表現されることが多く、バニリン様の甘さと特有の和菓子や花を思わせる香味を原酒に付与します。
オーク材と比較してタンニン量は少なく、樽としての主張は穏やかですが、その分ウイスキーのベース原酒の個性を損なわずに「和のニュアンス」「気品のある香り」を加える役割を果たします。
杉
杉樽とは、日本特産の針葉樹であるスギを素材とした熟成用樽を指します。
日本では古くから清酒や味噌・醤油などの発酵食品の木桶として使用されており、香り高く抗菌性に富んだ木材として伝統的に評価されてきました。
しかし、スギは一般的な熟成においては非常に限定的。鏡板のみ杉に変えるなど、現在でも試験的に使用がされています。
杉樽由来の香味の一部を紹介すると、
杉香、和風ハーブ、松、ローズマリー、緑茶
杉樽で熟成したウイスキーは、木材特有の和風な香気を顕著にまとい、他の樽では得られない清涼感と「木そのもの」を思わせる風味が際立ちます。「爽やかさ」「和の木香」を際立たせる効果があります。
4.入っていた酒類による香味プロセス
バーボン樽
バーボンウイスキーの製造に使用される樽は、アメリカンホワイトオーク製の新樽に限ることが、アメリカの連邦規定にて定められています。
この「新樽のみ」という制限により、アメリカにて役目を終えたバーボン樽は、世界中のウイスキー蒸溜所へと“第二の人生”を歩んでいます。スコッチやジャパニーズウイスキーでは、このリユースされたバーボン樽が熟成の中心的存在です。
アメリカンホワイトオークは、木材自体に豊富なリグニンやバニリン成分を含み、熟成を経てウイスキーに甘やかで厚みのある香味を与えます
バーボン樽由来の香味の一部を紹介すると、
バニラ、キャラメル、バナナ、焼き菓子等
セカンドフィルなどではまた香味がかなり変わってくることもあり、何度も使える上に、ブレンデッドや複数樽を使用したブレンドの世界では、この樽の個性が『味の骨格』として機能し、他の重厚なシェリーやミズナラ樽とバランスを取るのに必要不可欠です。
シェリー樽
シェリー樽とは、スペイン・アンダルシア地方で造られる酒精強化ワイン「シェリー」の熟成に使用されたオーク樽のことを指します。
シェリー酒の輸出用熟成には、500リットル級の大型の樽(バット)が伝統的に使われてきました。これらの空樽は、やがてウイスキー業界に渡ります。
使用されるオークは主にヨーロピアンオークであり、アメリカンオークと比べてタンニンが多く、抽出される香味もより重厚かつ複雑です。さらに、長年にわたりシェリー酒に使われてきたことで、樽材には豊富な糖分や酸化熟成由来の香り成分が染み込んでいます。
シェリー樽由来の香味の一部を紹介すると、
ドライフルーツ、ローストナッツ、カカオ、クローブ、革製品等
特にオロロソやペドロヒメネス(PX)といったタイプのシェリーを熟成した樽は、力強い個性をウイスキーにもたらします。こうしたシェリー樽の存在は、ブレンド構成において味わいに『奥行きと厚み』を加える重要な要素となります。
ワイン樽
ウイスキー業界におけるワイン樽とは、主に赤ワインや白ワインの熟成に使用されたオーク樽やその他の木樽。ウイスキーの熟成には、ワイン樽を用いることで、果実味豊かで華やかな香味を与えることができます。
近年、特にシェリー樽の入手が困難になってきている背景も含め、ワイン樽がウイスキー熟成に注目されており、多彩な香味の表現が可能です。
ワイン樽由来の香味の一部を紹介すると、
フレッシュベリー、チェリー、スパイス、タンニンの渋み、酸味
ウイスキーにおいては、赤ワイン樽は『果実味、ンニン由来の渋味』を与え、白ワイン樽はやや軽やかで華やかな『フローラル香』を付与する傾向があります。
また、日本のウイスキー業界では、国内のワイナリーの増加に伴い、提携先も増えたことでワイン樽熟成を積極的に取り入れる動きが広がっています。
ブランデー樽
ウイスキーにおけるブランデー樽とは、主にブランデーやコニャックなどの蒸留酒の熟成に使われたオーク樽のことを指します。ブランデーは果実(主にブドウ)を原料とするため、ウイスキーに用いることでフルーティかつ華やかな香味が付与されます。
ブランデー樽由来の香味の一部を紹介すると、
熟した果実、フルーツチョコレート、柔らかな酸味と樽香
ブランデー樽を使用したウイスキーでは、原酒に『厚みのある果実感と柔らかな甘み』が加わります。
ジャパニーズウイスキーにおいても、マルチカスクブレンドの一つとして、ブランデー樽が使用されています。100%ブレンデーカスクなどはいまだにお目にかかっていないものの、国内でもブランデーを作るメーカーがウイスキーを製造しているため、今後は増えてくるかもしれません。
ラム樽
ラム樽とは、サトウキビを原料とする蒸留酒「ラム」の熟成に使用されたオーク樽のことを指します。
カリブ海諸国を中心に生産されるラムは、その甘く濃厚な香味で知られており、使い終えたラム樽はウイスキー熟成においても「南国的な要素」を与える樽として注目されています。
ラムの熟成に使用される樽は、元バーボン樽が再利用されており、そこにラム酒が数年染み込んだ状態でウイスキー樽として転用されます。樽材には、糖蜜由来の香味やエステル香(バナナ、パイナップル等)がついています。
ラム樽由来の香味の一部を紹介すると、
焼きバナナや焼きパイナップル、トロピカルフルーツ、黒糖、ラムレーズン、カラメル、シナモン、糖蜜
ウイスキーにラム樽を用いると、陽性な甘みと南国フルーツのニュアンスが付与されます。香味の主張は強め。熟成期間は短めでも香りの移りが早く、フィニッシュ(後熟)で使用されることも多い樽です。
テキーラ樽
テキーラ樽とは、メキシコの蒸留酒「テキーラ」の熟成に使用されたオーク樽のことを指します。テキーラは、リュウゼツラン(ブルーアガベ)を原料とし、バーボン樽で熟成されることが多く、使用後のテキーラ樽にはアガベ由来の青っぽい香味や、柑橘系のニュアンスが染み込んでいます。
ウイスキーの熟成においてテキーラ樽は珍しい選択肢ですが、独特の香味特性が個性的なアクセントとなり、特にフィニッシュ(後熟)用途として注目されています。
テキーラ樽由来の香味の一部を紹介すると、
青ピーマン、土っぽいミネラル感、ハーブ
テキーラ樽は、原酒にキレのある青みと軽やかな柑橘香を与え、味わいをシャープに引き締めます。甘さに寄らない、ドライで草木的なフレーバーは、非常に面白いニュアンスを与えます。香味的にはかなり強い為、ピート原酒と合わせることが多い樽です。
焼酎樽
日本の伝統的蒸留酒、焼酎の熟成に使用された樽のことを指します。日本独自の酒類であり、熟成焼酎に関しても珍しいですが、その樽を再利用する試みは、日本の蒸溜文化とウイスキーを融合させた、革新的な樽。
使用される樽は多くの場合、オーク樽やバーボン樽が一般的。長期間焼酎に使用された後、独特の香味が樽材に染み込んでいます。これにより、熟成されたウイスキーには、焼酎特有の甘みや発酵香、香ばしいニュアンスが付与されます。
焼酎樽由来の香味の一部を紹介すると、
米飴、干し芋、香ばしい甘み、微かな麹香
その香味は大きなものではないですが、香ばしさと日本的な香りを与え、奥深い余韻を与える樽と言えます。
梅酒樽
梅酒樽とは、「梅酒」の熟成に使用された樽のことを指します。梅酒は日本国内で広く親しまれている伝統的な酒類であり、近年では本格的な熟成梅酒の製造も増えつつあります。その中で使用された樽が、主にフィニッシュ用ではありますが、ウイスキーの熟成に使用されています。
使用される樽は、もともとバーボンなどのオーク樽などを梅酒熟成に転用したものであり、長期間にわたり樽に染み込み、独特の和の香味成分が含まれています。
梅酒由来の香味の一部を紹介すると、
梅シロップ、杏、黒糖、酸味、プルーン、熟成感のある木香
ウイスキーにおいて梅酒樽を使用すると、まろやかで甘酸っぱいフルーツ感と、やや熟成した和菓子のような香りが加わり、味わいの余韻にふくらみと艶やかさをもたらします。個性が強いため、通常はフィニッシュ(後熟)に用いられますが、近年はウイスキー樽で梅酒を熟成してリリースする蒸溜所も増えているため、今後はその樽で熟成や追熟を行ったものが増えてくるかもしれません。
日本酒樽
日本酒樽とは、純米酒や貴醸酒寝かせた際に使用された樽のことを指します。日本酒自体は一般にステンレスタンクなどで貯蔵されることが多く、木樽による熟成は樽の他に木桶などが用いられています。
日本酒の樽熟成では、アメリカンホワイトオークやフレンチオークが使われることがあり、米のでんぷん由来の糖分やうまみ成分、日本酒酵母の代謝物が樽材に浸透しています。これらの成分がウイスキーに移ることで、穏やかな甘味と乳酸系の香味、そして和のニュアンスが加わります。
日本酒樽由来の香味の一部を紹介すると、
白桃、和梨、蒸し米、乳酸、酒粕の風味
ウイスキーにおいて日本酒カスクは、他のワイン系樽やシェリー樽とは異なる、『麹由来の果実と乳酸的なまろみ』をもった香味設計に寄与します。香りはライトなため、フィニッシュ(後熟)用途としての活用が主流です
マルサラ樽
マルサラ樽とは、イタリア・シチリア島で生産される酒精強化ワイン「マルサラ」の熟成に用いられた樽のことを指します。マルサラは、シェリーやポートと並ぶ33大酒精強化ワインの一つで、樽材には深い甘さと複雑な香味が浸透しています
マルサラ樽由来の香味の一部を紹介すると、
トフィー、オレンジピール、柑橘香、ナッツ、ロースト香
ウイスキーをマルサラ樽で熟成またはフィニッシュすると、これらの香味が強く移り、『リッチでスパイシー』な複雑さが加わります。色調も濃くなりやすく、醤油の様な深い琥珀色へと変化します
ポートワイン樽
ポートワイン樽とは、ポルトガル生産される酒精強化ワイン、「ポートワイン」の熟成に使用された樽を指します。ポートワインには「ルビー、タウニー、ホワイトなどのタイプが存在し、それぞれ異なる香味特性を持ちます。
ポートワインは甘口で果実味豊かな赤系ワインが主体で、ウイスキーにこの樽を用いると、濃密な果実香、赤い果実系の酸味、そして滑らかなタンニンが与えられます。
ポートワイン樽由来の香味の一部を紹介すると、
ブラックチェリー、イチジク、ダークチョコレート、黒糖
コチラも一般的にはフィニッシュ(後熟)用途として使われることが多く、ウイスキーに果実味・甘味・酸味の立体感を加える樽として知られています。シェリーよりもチョコレート感が強くなる印象です。
ビール樽
ビール樽とは、IPA(インディア・ペール・エール)やスタウトなどのクラフトビールの熟成・貯蔵に使用された樽を指し、近年使用が増えています。
ビールの熟成に使われた木樽には、ホップ由来の柑橘系の香味、麦芽の甘み、酵母による香気成分が残留しており、ウイスキーにそれらが移行することで、従来にない複雑な個性が生まれます。
ビール樽由来の香味の一部を紹介すると、
グレープフルーツ、ハーブ、スパイス、ホップの苦味、焙煎、ビール酵母由来の香り
一般的には「フィニッシュ」用途で使用されます。特にIPAやスタウトを熟成した樽は香味の主張が非常に強く、単体では使用されることのない樽とも言えます。
最後に
樽がもたらす、ウイスキーという芸術
ウイスキーの味わいは、原料や蒸留法だけでは語りきれません。その芯にあるのは、木がもたらす香味の骨格と、その木に染み込んだ“前歴”が育むニュアンス。
つまり、「木材」と「記憶」という二つが交差し、唯一無二の香りと味わいを編み上げているのです。
オークの種類によって与えられる骨格があり、そこにバーボン、シェリー、ワイン、日本酒、梅酒。
多彩な前歴が重なります。それぞれの樽が、木材の育った環境と個性、もうひとつの酒の記憶をまとい、そしてまたウイスキーを酒を育てるその営みは、まさに【時間と風味】の連綿と続く『継承』と言えます。
だからこそウイスキーは奥深い。一樽には物語と個性があり、一滴には感動とその余韻があるのだから。
最後に:ジャパニーズウイスキーのおすすめ書籍
世界的なトレンドを巻き起こしている「ジャパニーズウイスキー」の事をもっと知りたい、もっと勉強したいという方は、是非こちらの書籍をおすすめいたします。
(1).Whisky Galore(ウイスキーガロア)Vol.54 2026年2月号
巻頭は「スコッチ蒸留所名鑑」第4弾としてサントリーグローバルスピリッツの7蒸留所を大特集!
[特集]
◆日本のクラフト蒸留所最前線
火の神蒸溜所/マルス津貫蒸溜所/嘉之助蒸溜所
◆沖縄泡盛紀行
八重泉酒造/忠孝酒造/沖縄県酒造協同組合
◆世界でもっとも急成長を遂げるインドの「インドリ」ウイスキー
◆北アイルランドのウイスキー その特徴と10ブランドを紹介
[ブランド解説]
◆「ザ・ニッカ リミテッド」 次の100周年へ向かうニッカの“現在地”を表現
[イベントリポート]
◆初開催! ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2025
◆Whisky Festival 2025 in Tokyo
(2).ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー
世界的にも有名なウイスキー評論家で、ウイスキー文化研究所代表 土屋守先生の著書「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」です。
ウイスキーの基礎知識、日本へのウイスキーの伝来、ジャパニーズウイスキーの誕生、広告戦略とジャパニーズウイスキーの盛隆、そして、現在のクラフト蒸留所の勃興まで。日本のウイスキーの事が非常にわかりやすくまとめられた一冊。
(3).ウイスキーと私(竹鶴政孝)
日本でのウイスキー醸造に人生を捧げた、ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝。ただひたすらにウイスキーを愛した男が自らを語った自伝の改訂復刻版。若き日、単身スコットランドに留学し、幾多の苦難を乗り越えてジャパニーズ・ウイスキーを完成させるまでの日々や、伴侶となるリタのことなどが鮮やかに描かれる。
(4).新世代蒸留所からの挑戦状
2019年発売。世界に空前のウイスキーブームが到来しているいま、クラフト蒸留所の経営者たちは何を考え、どんな想いでウイスキー造りに挑んだのか。日本でクラフト蒸留所が誕生するきっかけを作った、イチローズ・モルトで有名なベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏をはじめとする、13人のクラフト蒸留所の経営者たちが世界に挑む姿を綴った1冊。
(5).ウイスキーライジング
2016年にアメリカで出版された『Whisky Risng』の日本語版であり、内容も大幅にアップデート。ジャパニーズ・ウイスキーの歴史が詳細に記述されているだけでなく、近年、創設がつづくクラフト蒸溜所を含む、日本の全蒸溜所に関するデータも掲載。そのほかにも、今まで発売された伝説的なボトルの解説や、ジャパニーズ・ウイスキーが飲めるバーなども掲載されています。
(6).ウイスキーと風の味
1969年にニッカウヰスキーに入社した、三代目マスターブレンダーの佐藤茂夫氏の著書。
『ピュアモルト』『ブラックニッカクリア』『フロム・ザ・バレル』の生みの親でもあり、なかでも『シングルモルト余市1987』はウイスキーの国際的コンペティションWWA(ワールド・ウイスキー・アワード)にて「ワールド・ベスト・シングルモルト」を受賞。
竹鶴政孝、竹鶴威の意志を引き継いだブレンダー界のレジェンドが語る今昔。