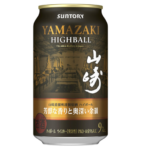遊佐蒸溜所。地酒「爽やか金龍」から世界を見据えたウイスキー「YUZA」の挑戦
山形県・鳥海山麓の町、遊佐。
ここにで静かに、しかし確かな意志を宿したウイスキー蒸溜所が稼働しています。
その名は遊佐蒸溜所。
一般見学こそ行っていないものの、「プロの方には必ず私が説明を行うんです。」と蒸溜所案内と説明は佐々木社長自らが。また常務の佐藤氏が同席するという体制からも、同所が単なる工場ではなく「真摯にものづくりをしている」企業であることが伺えます。
焼酎から始まった地元ブランド
蒸溜所の母体は、地元で長年親しまれてきた焼酎「爽やか金龍」。
サトウキビのモラセスアルコールとトウモロコシを原料に、他にはない個性を打ち出してきました。
県内のみの販売ながら強いブランド力を誇り、大手メーカーの価格競争にも巻き込まれず、酒販業者からも愛され、守られています。

しかし山形県は年間約1%ずつ人口減少が続いており、県内需要だけに依存すれば、シェアの縮小は明らか。
経営陣は20年以上にわたり新規事業を模索してきたそうです。
風力発電、サービス付き高齢者住宅、九州の焼酎工場買収などの案も浮かんでは消え、模索をしてきました。
転機は10数年前。
福島県 笹の川酒造・山口社長から、秩父蒸溜所のウイスキーが世界一を獲った話を聞いたことだった。「蒸溜所は2~3億円で建てられる」と知った佐々木氏は、県内市場を越え、世界を視野に入れる決意を固める。
立ち上げにあたって
建設当初の白塗の遊佐蒸溜所 画像引用:蒸溜所公式facebook
イチローズモルトの肥土伊知郎氏に話を聞くため、文化研究所の土屋氏を頼り情報収集。当時はあまり混んでいなかったウイスキーフェスティバルにて詳細に蒸溜所の建設について尋ね、両氏に知恵を借りた。
青写真を描いたうえで、佐々木氏が社長に就任した2017年に建設をスタート。2018年から製造を開始。
設備面では、当初は三宅製作所を検討したが実現せず、思いのほか早期納品が可能だったフォーサイス社製のスチル導入を決断。
2016年組からは少し遅れたものの、建設から製造までは国内では珍しいスピード感での立ち上げでした。
原料・設備管理
飲料メーカーとしての経験から、蒸溜所内はカードキーでセキュリティを強化。
外部からの異物混入防止を徹底している。
原料はポールズモルト社製を月1~2回、計15トンほど受け入れ、巨大な場内サイロで保管。
周囲は田畑に囲まれ、ヒメネズミが出るため、口に入るものを作る会社であるため、侵入が不可能なサイロにて原料を補完し、かなりの頻度で点検も行っている。
・スクリーン(石除去機):ドイツ製
・モルトミル:英国製
粉砕比率(ハスク:グリッツ:フラワー)は2:7:1に設定されている。
 |
 |
 |
 |
糖化・発酵の工夫
佐々木社長は長年、清酒や焼酎を造ってきたが、ウイスキー造りにあたっては「全てをリセット」して臨んだそう。一方で、品質管理や温度管理システムなどには、過去の経験も巧みに活かされています。
酵母は英国から月1回空輸されるオリジナルの「M酵母」。
発酵過程で死滅しやすく液中に溶け込みやすい性質があり、乳酸菌が爆発的に増えることで味わいがまろやかになる。木桶にて発酵されるが、発酵終了間際には「漬物のような香り」が立ち上ると佐々木社長は語る。しかしここまで行うことで味わいに深みを持たせ、後述の蒸溜機の造りにより、この[漬物のような香り]成分は取り除かれます。
糖化槽はステンレス製で、3番麦汁まで取り、3番麦汁は次回仕込みの温水として再利用。糖度の向上につながっています。
醪はアルコール度数7〜8%。ドラフは川口精機(静岡県清水市)の脱水機で処理し、近隣農家へ飼料として供給を行う。
発酵槽は日本木漕社製のカナダ産ダグラスファー。節の少ない木材を輸入し現地組み立て。木桶には発酵に有用な菌が棲みつく。発酵時間は昨年72時間から今年は96時間に延長。ただし「72時間の方がスタイルに合うかもしれない」とも。発酵は10〜30時間でピーク、35〜50時間で終了し、その後は乳酸菌発酵段階に移ると佐々木氏は語る。
 |
 |
 |
 |
蒸溜と廃熱の活用
スチルはフォーサイス社製。
・初溜器:マッカランを参考に設計
・再溜器:グレンドロナックを参考に設計
ネックは国内他蒸溜所と比べてもかなり長く、下向き。
この作りが前述の発酵過程における、硫黄除去率が高いとされる。カットはアルコール度数と官能検査に基づき、ローワイン、フェインツ、スピリッツを分ける。
スピリッツになるまでは何度も蒸留を繰り返し行い、無駄なくアルコールが収集できるように工夫がされています。
蒸溜廃液は熱交換器で再利用し、醪用仕込み水を30℃から60℃に温める。機械は高額で更新時期にあるが、コスト回収は未知数とのこと。山側にある遊佐では排水は処理を経て下水や農地利用が可能なほどになるそうです。
 |
 |
 |
 |
熟成・樽管理
熟成庫は蒸溜所横と鳥海山麓に2棟あり、計約4000樽を保管。一目で識別できるように樽は鏡板の色で管理されています。(白=1st fill、青=2nd fill、赤=3rd fill、黄=4th fill)。
リメイク樽に関しても有効活用を行っており、ある程度使用したものは有明産業で200Lを250Lにリメイクし、鏡板は新品に。過去にはスコットランドでのリメイク樽も使用していたが、返却された樽の品質が悪く以後依頼を中止している。
ミズナラ樽は新品1本40万円ほどとのこと。近年は漏れも少なく良好な品質。
県内限定「YUZA 朝日町ワインモデル」には年間5樽を使用し、瓶詰めを行い、県内に流通しています。
瓶詰め前にブレンドした原酒は、巨大なマリッジタンクに貯蔵。
樽からタンクに入れ、約21樽分がタンクにて寝かせられる。
シングルモルト「YUZA」や「シグネチャーブレンド」もマリッジタンクで寝かせてから瓶詰めが行われます。
瓶詰め設備もマリッジタンク倉庫内にあり、クリーンルーム仕様で冷房完備。他蒸溜所から羨望される造りとなっています。
ブレンド作成の際にはアルコール度数30%まで落として確認。
香りを重視し「香り7割:味3割」で評価している。
 |
 |
 |
 |
商品展開と味わい
現在の主力製品は
「シングルモルトYUZA」と「シグネチャーブレンド(モルト:国産グレーン=5:5、一部ピーテッド原酒使用)」。
国産グレーンは「仲間の蒸溜所」から供給を受けており、大切に扱われています。
「YUZA 2024」は“アーバンクール”をテーマに、都会の仕事終わりの一杯をイメージ。
バーボン樽比率は1st fill 20%、2nd fill 80%。
「遊佐6年」は初リリースのアプリコット香から、みかんのような柑橘香へ進化。100樽から十数樽を厳選し限定約7000本をリリース。
昨今は新しく、美味しい蒸溜所がたくさん出てきている。
遊佐はウイスキー事業への参入が早めだったこともあり、差別化の意味合いも込めてこの6年の味わいを出せている事を伝えたかったそうです。
今後は主力商品を主に、遊佐蒸溜所ファン向けに年に一度、スモールバッチで限定品を展開していくそうです。
 |
 |
 |
 |
組織・体制と哲学
蒸溜所スタッフは男女比5:5。スチル洗浄システムを導入するなど、効率化・省力化を進めている。
佐々木社長の言葉はどれも印象的。
・「リスペクトがあるからこそ伝統的な造りにこだわる」
・「良いものを造ることに手間暇とお金はおしまない」
その二つの信念は、蒸溜所の隅々に息づいていました。
他蒸留所からも信頼は厚く、伝統的ゆえに、工程に多くの人の手をかけているからこそ大規模蒸溜所などからの見学も多く、快く受け入れています。
他の蒸溜所から様々なアドバイスをいただくこともあり、社長はその多くを受け入れて、実際に試してみて落とし込んでいるそうです。
まとめ
静かなる志が、地元の風土を超えて世界へ。
遊佐蒸溜所のウイスキーは、その液体には確かな“哲学”が宿っています。
効率や規模よりも、「手をかけ、心を込める」こと。伝統を尊びながら、常に新しい挑戦を恐れないこと。
焼酎づくりで培った誠実で謙虚な精神と、世界を見据える広い視野。その二つが、山形県の遊佐という土地の中で融合しています。
「世界に誇れる日本のクラフトを、遊佐から。」
その言葉は決して派手ではないが、真摯なものづくりに携わる人々の姿勢そのものを表しています。
鳥海山から吹き下ろす風のように清らかで、静かな熱を内に秘めたウイスキー。
それが、ジャパンメイドのスコッチリスペクト 「YUZA」
この一滴から、山形の情熱と未来が、世界へ広がっていくことが楽しみです。
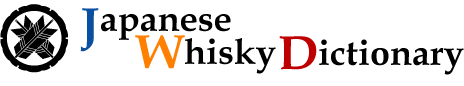

 建設当初の白塗の遊佐蒸溜所 画像引用:蒸溜所公式facebook
建設当初の白塗の遊佐蒸溜所 画像引用:蒸溜所公式facebook