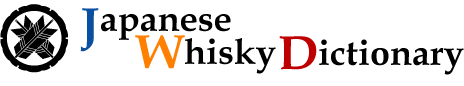ウイスキーの味わいを決定づける要素は、原料の大麦や熟成樽だけではありません。
仕込みや加水に用いられる「水」こそ、その土地の個性を最も端的に映し出す要素のひとつと言えます。
日本のウイスキーが世界的に評価される背景には、この国ならではの清らかな水の存在があります。
軟水と硬水を分ける指標は「硬度」であり、これは水1リットル中に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を炭酸カルシウムの量に換算したものです。
WHOの基準では、硬度60mg/L未満を軟水、60~120mg/Lを中程度の軟水、120~180mg/Lを硬水、180mg/L以上を非常な硬水と分類しています。
日本は山地が多く、年間降水量も豊富。
豊かな森が育む伏流水は、軟水が多く、またミネラル分が少なく、口当たりがやわらかい。
この水質は原材料の発酵を穏やかに進め、繊細で上品な風味を持つ原酒を生み出すのに適しているといわれます。
スコットランドで一般的な硬水においては、含まれるミネラルが酵母の栄養源となり、発酵が速く活発に進みます。そのため、糖分が効率よくアルコールに変換され、ドライで力強い酒質になりやすいといわれています。
1.日本の蒸溜所の水源紹介
1-1.山崎蒸溜所

サントリー山崎蒸溜所の「離宮の水」。硬度は約87mg/L中程度の軟水
昭和の日本名水百選にも選ばれた清らかな水が今も湧いており、データを取り続けている職人曰く、その品質は創業時と少しも変わらないものだそう。
豊臣秀吉が明智光秀を破った山崎の戦いにおいて、茶人・千利休がこの地を訪れて茶室を開くなど、歴史と由緒のある水。
硬度こそ中程度の軟水と言えますが、複雑で重厚なモルト原酒をつくるのに非常に適した性質を持っています。
1-2.白州蒸溜所

『南アルプスの天然水』という商品にもなっている白州蒸溜所の水。硬度は約30mg/L軟水
白州蒸溜所の仕込み水は、南アルプスの深い森に降った雨や雪が花崗岩層をじっくりと濾過して育んだ軟水です。硬度は約30mg/Lと非常に柔らかく、超軟水に近い性質を持っています。
また、白州の仕込み水は香りの立ちを良くし、スッキリと爽やかな味わいを引き出す特徴があり、清冽な森の息吹を感じさせるウイスキーづくりに欠かせない存在です。
1-3.余市蒸溜所

余市の仕込水は余市川の伏流水。硬度は20mg/L軟水と言われています。
積丹半島の付根に位置する余市は北に日本海を臨み、三方を山々に囲まれた地。冬の間に山に降り積もった雪は、春には雪解け水となって余市川に注ぎ込み、鮎が泳ぎ、鮭が遡上する地です。
竹鶴政孝氏がこの地を選んだ理由の一つにはこの豊富な水資源があることが挙げられています。
1-4.宮城峡蒸溜所

緑豊かな森に包まれた宮城峡。仕込水は蔵王連峰を経て流れてくる清らかな新川の伏流水。硬度は約20mg/Lの超軟水
日本各地の蒸溜所が使っている水の中でも硬度(公表値)が低く、ウイスキーづくりに邪魔な成分がほとんど含まれていません。
竹鶴氏は初めてこの地を訪れた時、新川の清流でブラックニッカを割って飲み、味わいを確認して蒸溜所建設を即決したと言われています。
1-5.厚岸蒸溜所

北海道厚岸蒸溜所では、アイラ島と同じ、ピートの層を通って流れるホマカイ川。その伏流水が蒸留所で使用されています。硬度は50ml/Lの軟水。
ラムサール条約の登録湿地、別寒辺牛湿原には何千年にも渡って蓄積されピート層があり、その層を通ってきた川の水は茶褐色。
仕込み水はもちろん浄水されていますが、まさにジャパニーズアイラともいえる水を使用し、今後は同じ厚岸の地のピートを使い、厚岸の水で育ち、厚岸の樽でつくられたオール厚岸ウイスキーの登場が待たれています。
1-6.Distillery “Water Dragon”(三島蒸留所)

静岡県の三島にあるDistillery “Water Dragon”。
厚生労働省指定の“おいしい水”や環境省指定の“名水百選”、国土交通省選定の”水の郷百選”にも選ばれる名水を使用。硬度は56mg/Lの軟水。自社水源の井戸水を使用しています。
三島では街のいたるところに清らかな富士山系の伏流水が湧き出ており、とても柔らかく澄み切った味わいが特徴。
ジャパニーズバーボンを目指す同蒸溜所は、アメリカのライムストーンウォーター(高度300mg/L)の超硬水に対し、この柔らかな水を使うことで日本らしさもあるバーボンスタイルを追求していく蒸溜所です。
1-7.天星酒造 菱田蒸溜所
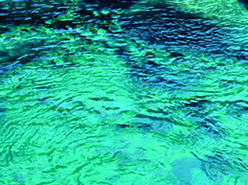
鹿児島県の菱田蒸溜所。
この地を流れる水は、平成の名水百選にも選定された「普現堂湧水源(ふげんどうゆうすいげん)」。
県内でも屈指の軟水として知られ、硬度は35mg/L。
シラス台地を通過して天然ろ過されることで非常にきれいで口当たりの良い水質を誇ります。明治の頃にはこの地に20ほどの焼酎蔵が集中していましたが、現在では天星酒造のみとなっています。
まとめ
この日本の水源を求めて、全国各地に数多くの蒸溜所や焼酎蔵、酒造が築かれてきました。
水と土地の個性を宿した酒造りは、まさにその土地の物語を映し出すものです。仕込みに使われる水は、香りや味わいの背後で静かに息づいています。
ウイスキーを口に含むと、その底には数十年という歳月をかけて、さらに数千年をかけて積み上げられた土壌を巡り抜けてきた、日本ならではの緑と山の多い水の旅路が潜んでいます。
当たり前のようにきれいな水を水道から飲める日本だからこそ、特別な水で仕込まれたジャパニーズウイスキーは、より一層特別に感じられるのです。
最後に:ジャパニーズウイスキーのおすすめ書籍
世界的なトレンドを巻き起こしている「ジャパニーズウイスキー」の事をもっと知りたい、もっと勉強したいという方は、是非こちらの書籍をおすすめいたします。
(1).Whisky Galore(ウイスキーガロア)Vol.54 2026年2月号
巻頭は「スコッチ蒸留所名鑑」第4弾としてサントリーグローバルスピリッツの7蒸留所を大特集!
[特集]
◆日本のクラフト蒸留所最前線
火の神蒸溜所/マルス津貫蒸溜所/嘉之助蒸溜所
◆沖縄泡盛紀行
八重泉酒造/忠孝酒造/沖縄県酒造協同組合
◆世界でもっとも急成長を遂げるインドの「インドリ」ウイスキー
◆北アイルランドのウイスキー その特徴と10ブランドを紹介
[ブランド解説]
◆「ザ・ニッカ リミテッド」 次の100周年へ向かうニッカの“現在地”を表現
[イベントリポート]
◆初開催! ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2025
◆Whisky Festival 2025 in Tokyo
(2).ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー
世界的にも有名なウイスキー評論家で、ウイスキー文化研究所代表 土屋守先生の著書「ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー」です。
ウイスキーの基礎知識、日本へのウイスキーの伝来、ジャパニーズウイスキーの誕生、広告戦略とジャパニーズウイスキーの盛隆、そして、現在のクラフト蒸留所の勃興まで。日本のウイスキーの事が非常にわかりやすくまとめられた一冊。
(3).ウイスキーと私(竹鶴政孝)
日本でのウイスキー醸造に人生を捧げた、ニッカウヰスキー創業者・竹鶴政孝。ただひたすらにウイスキーを愛した男が自らを語った自伝の改訂復刻版。若き日、単身スコットランドに留学し、幾多の苦難を乗り越えてジャパニーズ・ウイスキーを完成させるまでの日々や、伴侶となるリタのことなどが鮮やかに描かれる。
(4).新世代蒸留所からの挑戦状
2019年発売。世界に空前のウイスキーブームが到来しているいま、クラフト蒸留所の経営者たちは何を考え、どんな想いでウイスキー造りに挑んだのか。日本でクラフト蒸留所が誕生するきっかけを作った、イチローズ・モルトで有名なベンチャーウイスキーの肥土伊知郎氏をはじめとする、13人のクラフト蒸留所の経営者たちが世界に挑む姿を綴った1冊。
(5).ウイスキーライジング
2016年にアメリカで出版された『Whisky Risng』の日本語版であり、内容も大幅にアップデート。ジャパニーズ・ウイスキーの歴史が詳細に記述されているだけでなく、近年、創設がつづくクラフト蒸溜所を含む、日本の全蒸溜所に関するデータも掲載。そのほかにも、今まで発売された伝説的なボトルの解説や、ジャパニーズ・ウイスキーが飲めるバーなども掲載されています。
(6).ウイスキーと風の味
1969年にニッカウヰスキーに入社した、三代目マスターブレンダーの佐藤茂夫氏の著書。
『ピュアモルト』『ブラックニッカクリア』『フロム・ザ・バレル』の生みの親でもあり、なかでも『シングルモルト余市1987』はウイスキーの国際的コンペティションWWA(ワールド・ウイスキー・アワード)にて「ワールド・ベスト・シングルモルト」を受賞。
竹鶴政孝、竹鶴威の意志を引き継いだブレンダー界のレジェンドが語る今昔。